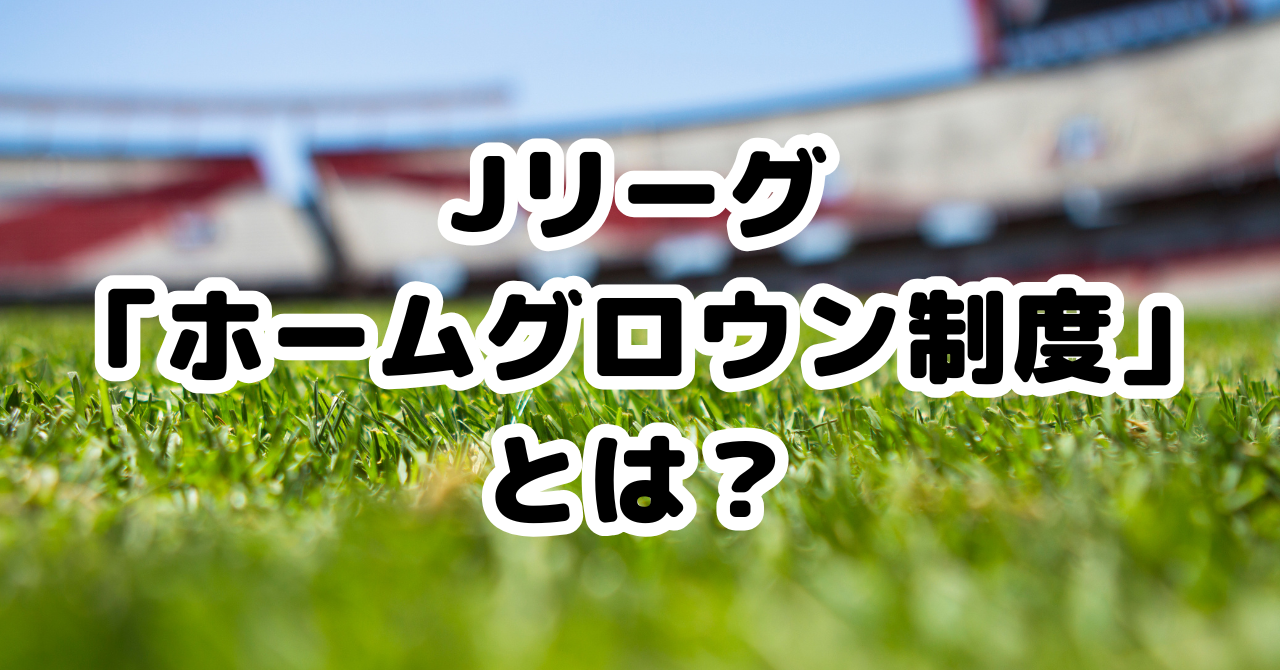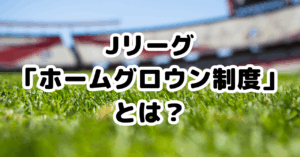Jリーグは、2025年7月29日に開催した理事会で、2026年1月から同年6月の2026特別シーズンのホームグロウン制度を現行のホームグロウン基準人数を継続することが決定しました。
ホームグロウン制度は、Jリーグクラブが自前で育成した選手をトップチームに登録するための制度です。
この制度によって、クラブはアカデミー強化にコミットし選手育成の土壌作りを進めることになります。
ホームグロウン制度 なぜこの制度がいま求められているのか?
Jリーグには、地元出身やクラブ育成選手への期待があります。
しかし、従来は外部スカウトによる補強が優先され育成選手の出場機会やキャリア形成が後回しになりがちでした。
現場指導者から聞いた言葉があります。
「育成費を投じても結果が目に見えにくいと、経営判断が揺らいでしまう」そういった課題にこそ制度が光を当てています。
東京のユースチームに所属する選手の保護者の方は、「うちの子が、利き足や技術ではなく、ホームグロウンとして認定されてトップに上がる日を夢見て頑張っています」
この制度があることで、選手や家族にとって“明確な目標”ができることが大きな意義です。
ホームグロウン選手の定義とは?
12歳の誕生日を迎える年度から21歳の誕生日を迎える年度までの間に対象クラブの第1〜第4種チームに通算で990日以上登録されていた選手、これがJリーグが定めるホームグロウン選手です。
990日は、だいたいJリーグの3シーズン分に相当します。
ただし、“在籍しただけ”では不十分で登録された“日数”が基準です。
実際には、試合出場なくても、登録が続いていれば日数は積み上がります。
さらに細かいルールとして、期限付き移籍中の期間は「移籍元クラブ」で計算され、特別指定選手として他クラブに登録されている場合はカウント対象外となります。
これらは制度本来の意図を守るための条件設計です。
ホームグロウン制度 登録義務と罰則ルールの概要
Jリーグの各クラブは、トップチーム登録ウインドー終了時に一定数以上のホームグロウン選手を登録しなければなりません。
- J1では最低4名
- J2・J3では最低2名
該当シーズンに人数が不足した場合は、翌シーズンにおけるプロA契約可能選手枠が未達分だけ減らされる罰則が科されます。
例えばJ1であと1人足りなければ、翌シーズンに1人少ない契約しかできなくなる、という仕組みです。
ただし、2026年の特別シーズンではこの罰則制度は一時的に除外される方針が決まっています。
ホームグロウン制度スタートから現在までの流れ
この制度は2019年に導入され、当初はJ1のみ適用、規定人数2名から始まりました。
その後段階的に上昇し、2022年からJ1で4名規定に到達。
J2・J3においても、2023年から最低2名義務化されました。
導入当初の年は、「本当に育成選手を出せるのか?」といった慎重な声もありました。
ですが、鹿島アントラーズやFC東京など伝統クラブを中心に実際に10人以上のホームグロウン選手をトップ登録するクラブも現れました。
一方でアカデミー整備に遅れた地方クラブでは、義務者数を達成できずに罰則に直面するケースもありました。
ホームグロウン制度の実態>2025シーズンの登録状況
Jリーグは2025年シーズンにおいて、J1チームが平均6〜8人のホームグロウン選手を登録しており、FC東京は最多の15名、鹿島・広島は13名登録という報告があります。
一方で、J2のいわきFCや藤枝MYFC、J3では八戸や奈良クラブなど、未達のクラブも複数あり、トップ指導者からは「資源が限られていて苦しい」との声も。
これらをまとめると、都市圏クラブは制度を活かす余裕があり、地方クラブにはまだ制度対応の負荷が大きい様子が見てとれます。
各クラブのホームグロウン選手人数
※カウント基準日(第1登録ウインドー終了の3月26日)
※2025シーズンの基準人数 J1:4人、J2/J3:2人
▽J1
鹿島:13
浦和:7
柏:12
FC東京:15
東京V:9
町田:4
川崎F:11
横浜FM:9
横浜FC:4
湘南:8
新潟:7
清水:7
名古屋:5
京都:8
G大阪:8
C大阪:7
神戸:6
岡山:2
広島:13
福岡:5
合計:160▽J2
札幌:8
仙台:4
秋田:2
山形:4
いわき:0
水戸:1
大宮:11
千葉:5
甲府:7
富山:2
磐田:6
藤枝:0
山口:2
徳島:3
愛媛:3
今治:2
鳥栖:7
長崎:5
熊本:4
大分:7
合計:83▽J3
八戸:0
福島:0
栃木SC:3
栃木C:0
群馬:1
相模原:0
松本:9
長野:3
金沢:2
沼津:8
岐阜:1
FC大阪:0
奈良:1
鳥取:2
讃岐:2
高知:0
北九州:4
宮崎:0
鹿児島:2
琉球:2
合計:40

ホームグロウン制度にはどんな効果があったのか?
ホームグロウン制度導入により、クラブは“育成の投資対効果”を実感し始めました。
アカデミーを整備すればするほどトップ契約者が増え、サポーターや地域の誇りにも繋がります。
一部クラブでは、地元出身選手が活躍することで観客動員が増えた例もあります。保護者へのインタビューでは「子が活躍して嬉しい」との声も。
ただし、制度による縛りで契約や補強の自由度が制限されると感じるGMもおり、「即戦力を第1に考えるか、育成を重視するか」の舵取りが課題です。
誤解しがちなポイント:注意すべき点
- HG選手と、3年以上下部組織出身という区別
- 特別指定選手制度はカウントされないこと
- 移籍中の育成日数の扱い/(期限付きは元所属で計算)
これらについては細かく解説することで、誤解を避け、正確に理解できます。
ホームグロウン制度 よくある質問
- ホームグロウン選手と下部組織出身者はどう違う?
-
下部組織出身者は、3年以上そのクラブで活動すればある程度優遇される制度ですが、HG制度は「990日以上の登録日数」に基づく公式制度です。
- 期限付き移籍中の育成日数はどうなる?
-
育成期間は移籍元クラブで積算され、移籍先では対象外です。
- プロA契約枠の制裁は本当に2026年は撤廃?
-
はい。2026年特別シーズンに限り罰則(プロA契約枠減少)は適用されない方針がJリーグ理事会で決定されています。
ホームグロウン制度の未来と課題まとめ
- 育成選手の活躍はクラブのブランドにもなる
- 都市部クラブと地方クラブの格差是正が必要
- 制度が進化し、Jリーグ全体の育成力向上につながることを期待
今後も、2027年以降の制度改定やクラブの育成戦略を見ることで日本サッカー界の次のステップを感じられるはずです。
ホームグロウン制度まとめ:育成と地域愛を繋ぐ制度の本質
ホームグロウン制度は、単なる制度ではなく、「クラブと地域をつなぐ未来への約束」です。
制度を理解し、クラブが、選手が、保護者が、一体となって育成に向かう未来の姿を描いてみてください。