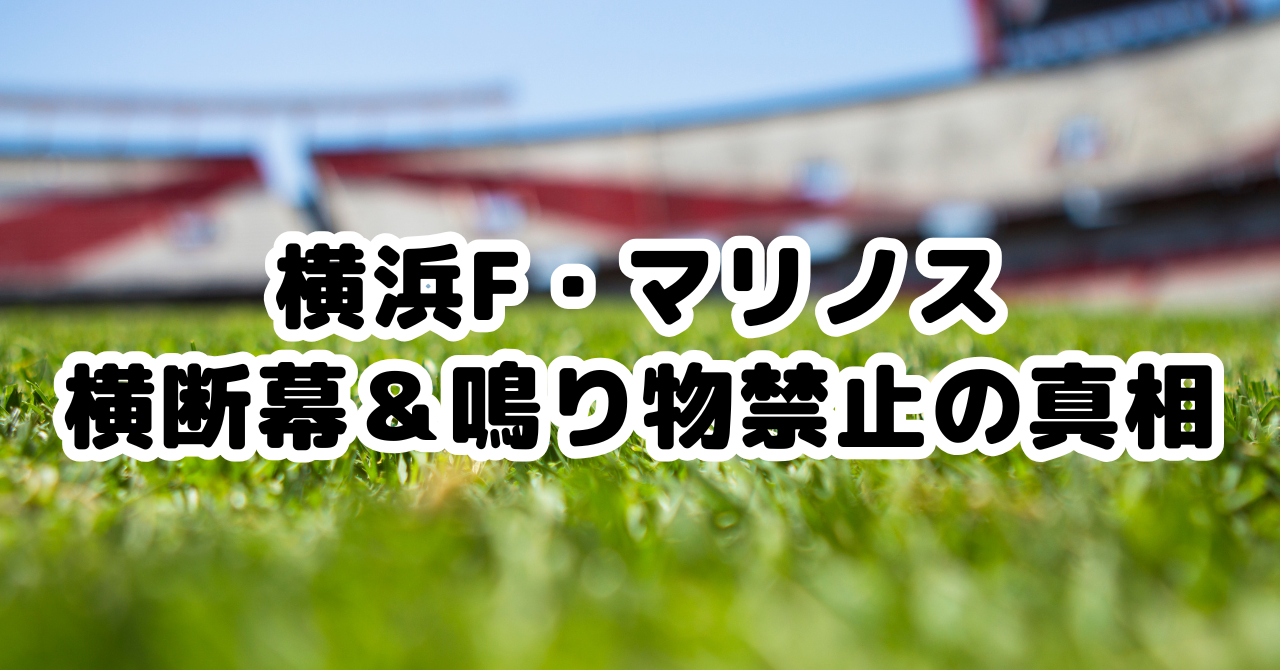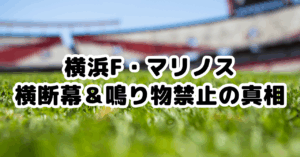何でマリノス 横断幕&鳴り物禁止?
- 2025年7月5日の横浜FC戦で発煙筒・花火使用などの規律違反が発生
- 59名に無期限入場禁止処分、4サポーター団体に活動禁止措置
- 7月20日以降、全公式戦・全エリアで横断幕・鳴り物使用を禁止に
- 8月9日、明治安田J1第25節・東京ヴェルディ戦でも禁止措置下での試合へ
- 現場では公式グッズのみ使用可能だが、応援の工夫が求められる状況に
静かなスタンドに立った夜
2025年8月9日、味の素スタジアムに立った瞬間、胸の奥が少し締め付けられた。
18時03分、試合開始の笛が響くが、そこにあるはずの太鼓の重低音も、ラッパの高鳴りもない。
視界の先には、かつて誇らしく並んでいた横断幕が一枚もなく、空いたスペースが妙に広く感じられた。
それでも、沈黙の中から自然に手拍子が生まれ、少しずつスタンド全体に広がっていく。
チャントは鳴り物に頼らない分、ひとつひとつの声がはっきりと響き、選手へ直接届いていくようだった。
いつもの熱狂は失われたが、この夜の応援には、逆境の中でもクラブを支え続ける覚悟と一体感が確かに宿っていた。
禁止措置の発端──7月5日の横浜ダービー
2025年7月5日、ニッパツ三ツ沢球技場。
横浜FCとの“横浜ダービー”は、本来なら街を二分する熱戦とサポーターの声援で彩られるはずだった。
しかしその日、一部の横浜F・マリノスサポーターが発煙筒や花火を使用し、さらに集団で相手を挑発する行為が発生した。
赤い煙が立ちこめ、火花が散る光景に周囲の観客は驚きと不安の表情を浮かべた。
子どもを抱えた親が席を離れる姿もあり、スタジアムの空気は一気に緊張へと変わった。
これはJリーグ共通観戦マナー&ルールの根幹を揺るがす重大な違反であり、クラブの信用をも傷つけるものだった。
クラブは試合後すぐに調査を開始し、関与した59名を無期限入場禁止処分に。
さらに、活動を想起させる行為が確認された4つのサポーター団体にも無期限活動禁止措置を下した。
これほど迅速かつ厳格な対応は、クラブの歴史においても異例と言える決断だった。
全エリア・全公式戦での禁止措置決定
処分発表からわずか2日後、クラブはさらに大きな一歩を踏み出した。
その内容は、横浜F・マリノスが出場するすべての公式戦において、ホーム・アウェイの区別なく、全てのエリアで横断幕や旗、ゲートフラッグ、太鼓やトランペットなどの鳴り物の持ち込み・使用を禁止するというものだった。
この決定は、サポーター文化の象徴ともいえる応援スタイルを一時的に断つことを意味する。
クラブ関係者によれば、「安全と秩序を最優先に考えた結果」であり、試合会場での安心感を取り戻すためには避けられない選択だったという。
応援を支えてきた多くの人々にとっては苦渋の決断だったが、それでもこの措置は、未来のスタジアムを守るための“痛みを伴う改革”として受け止められた。
第25節・東京ヴェルディ戦──禁止下での応援現場
2025年8月9日、味の素スタジアムに集まった観衆は26,902人。
湿気を帯びた夏の夜、横浜F・マリノスはリーグ再開後3連勝を狙い、東京ヴェルディとのアウェイ戦に臨んだ。
しかし、スタンドには横断幕も太鼓もなく、鳴り物禁止の静かな空気が広がっていた。
試合は序盤から一進一退の展開が続くも、62分、ヴェルディの谷口栄斗がゴール前の混戦から冷静に決め、先制点を奪う。
この一撃が勝敗を分け、横浜FMは0-1で悔しい敗戦を喫した。
試合後、応援席では「声だけで選手を支え続けた」という達成感と、「結果で応えられなかった」という悔しさが入り混じった表情が多く見られた。
禁止措置の中でも、サポーターは最後まで立ち上がることなく声援を送り続けていた。
サポーター席の空気
8月9日の味の素スタジアム。スタンドには一切の横断幕がなく、太鼓やラッパといった応援の象徴も姿を消していた。
その代わりに、キックオフ直後から自然と手拍子が起こり、やがてチャントが波のように広がっていく。
音響や装飾に頼らない、まさに“原点”ともいえる応援スタイル。
その静けさは、禁止措置がもたらした現実を雄弁に物語っていた。
サポーターの声
試合後、ゴール裏にいた30年来のベテランサポーターは、疲れ切った声でこう話してくれた。
「もっと色や音で選手を後押ししたかった。でも今はこれで守るしかないんだよ。応援の根っこは俺たちの声にある。」
ピッチ上でも、選手たちの表情には悔しさが滲んでいた。
後半途中から出場した渡辺皓太は「勝ちにいってたのに結果が出ず残念」と振り返り、天野純も「守備で噛み合わず、相手に押されてしまった」と静かに語った。
勝敗と同じく、この日の空気もまた、簡単には忘れられないものになった。
なぜここまで厳しい対応なのか
Jリーグ共通観戦マナーでは、発煙筒や花火の使用は明確に禁止されている。
理由は単純で、それらは視界を遮り、煙によって呼吸困難や転倒の危険を生むからだ。
さらに火薬を伴う火器は、火災や火傷といった重大事故を引き起こす可能性を常に秘めている。
加えて、集団による挑発行為は群衆心理を刺激し、衝突や暴力に発展しかねない。
スタジアムは家族連れや子どもも訪れる場所であり、安心して観戦できる環境の維持は絶対条件だ。
安全と秩序の確保は、クラブ経営において最も優先すべき課題のひとつ。
これを軽視すれば、試合運営はもちろん、クラブの信頼そのものが揺らぐことになる。
だからこそ横浜F・マリノスは、応援文化の一部を犠牲にしてでも、この厳しい措置を選ばざるを得なかったのだ。
観戦時に知っておくべきポイント
現在の横浜F・マリノス戦では、応援スタイルに関して明確な制限が設けられている。観戦を予定しているなら、次のポイントを必ず押さえておきたい。
1. 応援グッズは公式グッズのみ使用可能
クラブが販売・配布した旗やタオル、トリパラなどは使用できるが、市販品や自作の旗・タオルは全面的に禁止されている。
2. 鳴り物の使用は禁止
太鼓、ラッパ、拡声器など、音を出す応援アイテムは一切持ち込み不可。
声援や拍手での応援が基本となる。
3. 手拍子とチャントの創意工夫が重要
音響に頼らない分、手拍子のリズムや声の重なりが一体感を生み出す鍵になる。
4. ミックスエリアも例外なし
このルールはホーム、アウェイを問わず、すべての観戦エリアで適用される。
試合当日、ルール違反となれば入場制限や退場措置が取られる可能性もあるため注意が必要だ。
サポーター文化と安全規律の狭間で
横浜F・マリノスの応援文化は、日本サッカー界でも屈指の存在感を誇る。
ゴール裏を覆い尽くす大旗、太鼓の重低音に合わせた力強いチャント。
それらは選手の背中を押し、スタジアム全体をひとつに染め上げてきた。
この色と音は、単なる演出ではなく、クラブの歴史と誇りそのものだった。
しかし、情熱が形を持つとき、時に安全との衝突が避けられない瞬間が訪れる。
ルールを守ることと、文化を守ることが同時に叶わないなら、一時的な犠牲を受け入れる覚悟が必要になる。
今回の禁止措置は、応援文化を削ぐためのものではない。
むしろ、安全に応援できる未来を築くための“守りの一手”だ。
この選択があるからこそ、再び色と音に満ちたスタンドを取り戻せる日がやってくると、多くのサポーターが信じている。
横浜F・マリノス 基礎データ(再掲)
- 創設:1972年(前身:日産自動車サッカー部)
- ホーム:神奈川県横浜市、日産スタジアム
- J1リーグ優勝回数:5回(直近2022年)
Q&A
Q1. 禁止措置はいつまで続く?
A. クラブは「当面の間」継続とし、明確な解除時期は未定。
Q2. アウェイ戦でも同じ禁止?
A. はい。全公式戦・全エリア共通の運用。
Q3. 応援スタイルを変えるヒントは?
A. 手拍子、チャント、声援が今できる最大の応援手段。工夫ある応援を。
まとめ
7月5日に起きたサポーターによる違反行為は、クラブの強硬な対応を招いた。
その結果、横断幕も鳴り物も消えたスタンドが8月9日に繰り広げられ、「静かでも強い応援」の形が浮かび上がった。
応援とは音や色だけではなく、心をひとつにする“声の重なり”であることを、サポーターとクラブと選手が再確認した一戦だった。
それでも、スタンドがまたかつての色と音に溢れる日を、みんなが信じて前を向けるように──そんな願いと覚悟が、この静かな夜に込められているのです。